エアコンの選び方・畳数の決め方やAPFでチェックする省エネ性能など
日々の生活に欠かせないエアコン。しかし購入しようと思って検討すると知らないことばかり。
ということでエアコンの選び方について今回はまとめてみたいと思います。
エアコンのタイプ
エアコンというと壁に取り付けられている横長の壁掛けタイプがありますが、窓用や床に置いて使うタイプがあります。知っている人も多いかもしれませんが一応チェックしてみましょう。
壁掛け

一番一般なタイプです。種類が多く選択肢も広いです。
ご存知のように室内機と室外機があって配管で繋ぐ必要があります。
窓用
窓に設置することができるエアコンです。室外機を設置する必要が無いのでスペースの限られた場所でも設置が可能で工事の手間も壁掛けにくらべると少なく済みます。
自分で取り付けたという人も。
選べる機種の数という面では壁掛けに劣ります。
床置き
床に置いて使うタイプ。壁掛けのように高いところから吹き付けるのではなく低い位置から空気を送り込むので人がいる場所に効率的に空気を送ることができるというメリットがあります。が、機種の選択肢は壁掛けに比べて少ないです。
対応畳数の表記をそのまま信じるな!
エアコンのカタログには「おもに8畳用」なんてことが書かれていますが、「うち8畳だからこれでいいやー」なんてあっさり決めてはいけません。もっとよく表示を確認してもらいたいのですが、

よくみたらこんなことが書かれています。これは7~10畳の部屋全てに対応しているというわけではなく、建物の構造によって冷暖房の効率が違うのでこのように表記されているんです。
例えば木造で南向きの部屋は冷房は7畳まで、鉄筋コンクリートの部屋なら10畳といった具合です。
木造住宅は鉄筋コンクリートの建物より効率が落ちますし、南側は太陽熱の影響を受けやすいというわけです。また、冷房と暖房とでは暖房のほうが対応畳数が狭くなる傾向にあります。よってこうした要素を考慮して選ばなければなりません。
この表記の目安ですが、数字の小さいほうが木造南向きで使用するとき、大きいほうが鉄筋コンクリートの南向きの部屋で使用するときの目安となります。
部屋の構造にも注意して!

部屋が吹き抜けの場合は天井が高いため、よりパワーが必要になりますし、キッチンで使う場合もコンロという熱源があるためパワーが必要になります。
吹き抜けの場合は広にもよりますが、キッチンの場合は対応畳数よりも4畳は広い部屋に対応したエアコンを選ぶのが良いといわれています。
省エネ性をチェックしよう

省エネ性を見極める指標としては省エネ基準達成率とAPFというものがあります。
省エネ基準達成率
目標基準値が設定されていてその達成率を星5つで表すのでわかりやすいですが、室内機と室外機の寸法やエアコンのパワーなどの区分があるので、同じ区分のエアコン同士で比較しないと正しい判断ができません。
年度も基準があって20○○年度版などと表示されています。
APF(通年エネルギー消費効率)
このAPFという数値はある一定の条件下でエアコンを運転した際の消費電力1キロワットあたりの冷暖房能力を表すものです。
この数値が大きいほど効率に優れているのでこちらのほうが他のエアコンとの比較がしやすいでしょう。
算出条件についてもっと詳しく知りたい方は日本冷凍空調工業会のページを参考にしてください。
エアコンのパワーをチェックしよう

エアコンのスペックを見ていると「○.○kW」という表記があります。これは何を表すのかというと冷暖房の能力を表しています。数値が高いほど能力が高く広い部屋でもエアコンを効かせることができます。
カッコ表記で(0.8~5.7)といった表示もされており、これは運転時のパワーの範囲を表しています。数値の幅が広いほどパワー調節の幅が広いということです。
寒冷地で使うなら低温暖房能力をチェック
寒い地域で塚ならば低温暖房能力についてもチェックしておきましょう。外気温2℃のときにどのぐらいの暖房パワーを発揮できるかを表すものです(通常表記されているもの外気温7℃)。
kWで表記され、この数値が高いほどパワーを発揮できることを示しています。
使用環境に応じてモデルの使い分けを

各メーカーエアコンのラインナップはかなり細かい区分けがあるのですが大きく3つに分けると、
- センサーやフラップの機能が充実したフラッグシップモデル
- 自動お掃除機能を搭載したり運転モードが充実したりしているミドルモデル
- 最低限の機能を備えたベーシックモデル
といった感じになります。
細かいところは個人の好みにもよりますが、フラッグシップモデルは機能が充実しているので使用時間が長く複数の人数で過ごすリビングに、寝室にはミドルモデル、使用頻度の低い部屋にはベーシックモデルといったように部屋の用途に応じて購入するエアコンを変えるのがよいでしょう。
あえてベーシックモデルを好む人もいる

自動お掃除機能は完全に取り切れないゴミもありますし、余計な機能があると故障しやすいといってあえてベーシックモデルを買う人もいます。
故障するかどうかは運の要素もあるものの、わずかでも故障の確率が下がるならベーシックモデルにするというのも1つの手です。
普段エアコンフィルターの掃除をする習慣の無い人は冷暖房の効率が落ちるので自動お掃除機能があったほうがいいですが、こまめに掃除をする人はお掃除機能の無いモデルを選ぶのもありかもしれません。


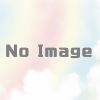




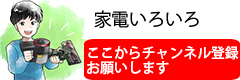
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません